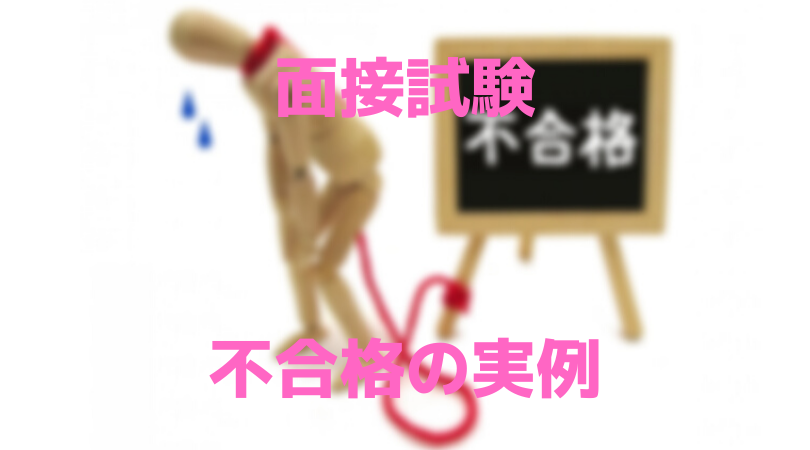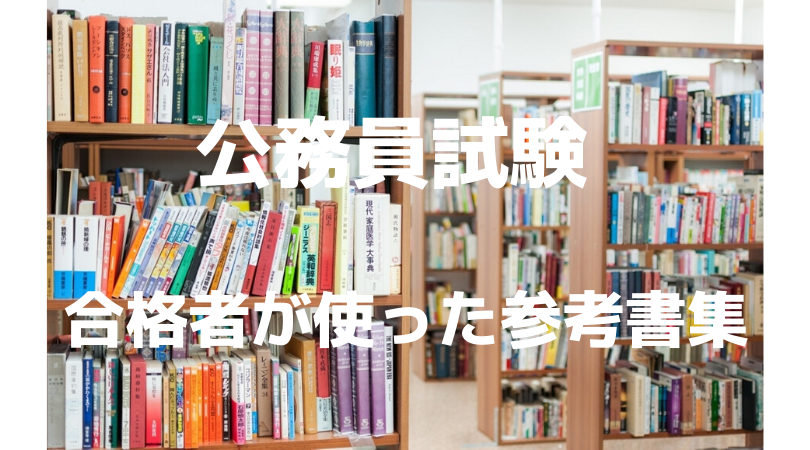こんな疑問に答えていきます。
✔️本記事の内容
- 社会人から公務員になる方法
- 【試験別】必要な勉強時間
- 公務員になるためにすべき行動
こんにちは、元公務員のはやたです!
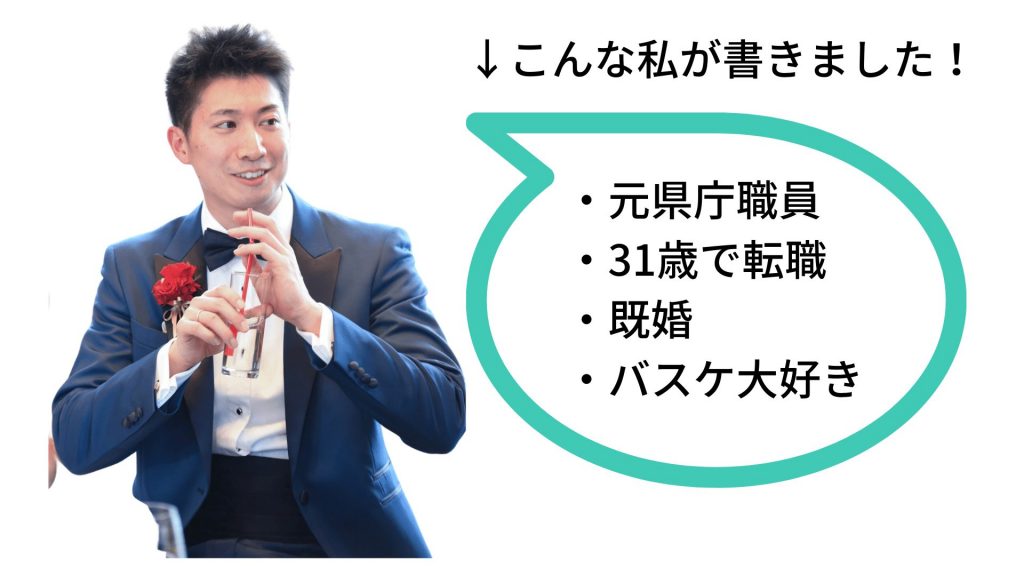
この記事を書いている僕ですが、9年間地方公務員として勤め上げ、現在は中堅の民間企業でWebの仕事をしています。
公務員試験は現役で合格し、民間への転職経験もあるので、会社員と公務員それぞれの視点で有益な記事を書いています。
今回の記事では、社会人が受ける公務員試験の勉強時間と内容について解説しています。
社会人から公務員になる方法

社会人から公務員を目指す場合、ルートが2つありまして、年齢によって受けられる試験区分が決まっています。
どちらの試験を受けるかによって勉強時間と内容が大幅に変わるので、とても重要な点です。
30歳以下:大卒程度試験を受ける
行政機関や自治体ごとに差はありますが、概ね30歳以下は大卒程度試験を受けることになります。
要は新卒組と同じ試験ですね。
国家公務員の事例を見てみましょう。
国家公務員一般職(大卒者)
2021年7月に行われた国家公務員一般行政職の試験概要です。
ちなみに、2020年度の試験の試験結果は下記の通りでした。
- 受験者数:28,251人
- 最終合格者数:6,031人
- 最終倍率(受験者数÷最終合格者数):4,68倍
31歳以上:社会人経験採用試験を受ける
こちらも行政機関ごとに差はあるのですが、概ね31歳以上の場合は社会人経験採用試験を受験します。
名古屋市行政職(社会人試験)
名古屋市の試験概要を見てみましょう。
基本的に社会人採用試験の場合、筆記試験に専門科目はありません。
ちなみに、2020年度の試験の試験結果は下記の通りでした。
- 受験者数:384人
- 最終合格者数:19人
- 最終倍率(受験者数÷最終合格者数):20.2倍
大卒者向けの試験よりも倍率がかなり高いことがわかります。
【試験別】必要な勉強時間

大卒程度と社会人経験採用試験の大きな違いは、専門科目の有無です。
専門科目は教養科目に比べて難易度も高く、範囲も広いため勉強時間を多く取る必要があります。
この専門科目の有無が、そのまま勉強時間の量の違いとなります。
大卒程度試験を受ける場合
ずばり、1,000時間が必要です。
これは私が実際に行った勉強時間で、一つのボーダーラインだと考えられます。
内訳としては、教養300時間、専門700時間程度です。
専門試験は範囲が広い上に配点の比率も高いので、重点を置いて学習をする必要があります。
社会人採用試験を受ける場合
社会人採用試験の場合は、教養科目300時間程度、論文50時間程度でOKです。
教養科目は専門科目と異なり、一定のレベルに達したらあとは勉強しても変わらなくなります。
その一定のレベルに達するまでの時間が300時間です。これも私の実際の勉強時間ですが、周りの職員も同じような作戦だったので間違いありません。
よくある質問:仕事は続けるべきか
実際のところ、社会人が仕事をしながら勉強することはかなりハードです。
現実問題として、仕事をしながらでも300時間程度ならばなんとかなるが、1000時間は無理だと思います。
下記にモデルを示すので、参考にしてみてください。
過去の職場でも社会人から公務員試験を受けた人が数人いたので話を聞きました。大卒程度の試験を受けた人は全員退職して勉強、経験者採用の人は仕事をしながら受験したとのことでした。
勉強スケジュール(平日)
| 7:00 | 起床 |
| 9:00 | 出社 |
| 18:00 | 退社 |
| 19:00 | 帰宅、夕食、入浴 |
| 21:30 | 勉強開始 |
| 23:30 | 勉強終了 |
| 24:00 | 就寝 |
勉強時間:2時間
ブロガーやってるのでわかりますが、出勤日に1日2時間確保するのは超ハードですよ。
最近は在宅勤務もあるので、その場合は通勤がない分勉強しやすいかもしれませんね。
勉強スケジュール(休日)
| 8:00 | 起床 |
| 10:00 | 図書館着、勉強開始(2.5h) |
| 12:30 | 昼休み |
| 13:30 | 勉強再開(3.5h) |
| 17:00 | 閉館、図書館発 |
| 18:00 | 帰宅、夕食、入浴 |
| 21:00 | 勉強開始(2h) |
| 23:00 | 勉強終了 |
| 23:30 | 就寝 |
勉強時間:8時間
学生時代の私もこんな感じでした。
休憩時間に缶コーヒー飲んだり、少し周りを散歩することが少ない楽しみでしたね(苦笑)
公務員になるためにすべき行動

公務員に転職するために重要な行動は、ズバリ情報収集です。
今までに説明したように、公務員試験は受験科目や受けられる試験区分、受験日が決まっています。
そして、この試験の時期や受験科目は毎年変わりません。
きちんと情報を集めておくことで、効率的な試験対策を行うことが可能なのです。
そのため、公務員への転職は情報収集がとても重要になります。
公務員に転職する際に必要な情報
公務員への転職に必要な情報ですが、下記の通り。
- 公務員の種類
- 試験区分&受験資格
- 試験科目
- 試験スケジュール
- 試験の難易度
少なくとも上記の情報を集める必要があります。
しかしながら、これらの情報を仕事をしながら集めることは相当な負担ですよね。
この問題を1発で解決するのが、「公務員転職ハンドブック ![]() 」です。
」です。
【勧誘なし】公務員転職ハンドブックとは

クレアール:社会人のための公務員転職ハンドブック
大手予備校の「クレアール」さんが出している資料で、下記の内容がまとまった60ページほどの冊子です。
- 公務員の仕組み(受験資格・試験区分・職種)
- 試験スケジュール
- 転職ルート
- 教養試験の過去問
- 論文試験の過去問
- 面接試験の解説
- 社会人採用試験の過去データ(受験資格・試験科目・倍率・初任給)
- 転職Q&A
- 合格体験記
この資料を読み込むと、公務員になるためのロードマップが見えてきます。
特に社会人採用試験の過去データと過去問が集まっているのは大変ありがたいですね。それだけでも十分価値があります。
ちなみに資料は「無料」でして、電話での勧誘もなし(電話入力不要)です。
公務員になるためには1日でも早く行動した人が有利なので、まずは情報を集めるところから始めましょう。
ハンドブックの詳細がもう少し知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。